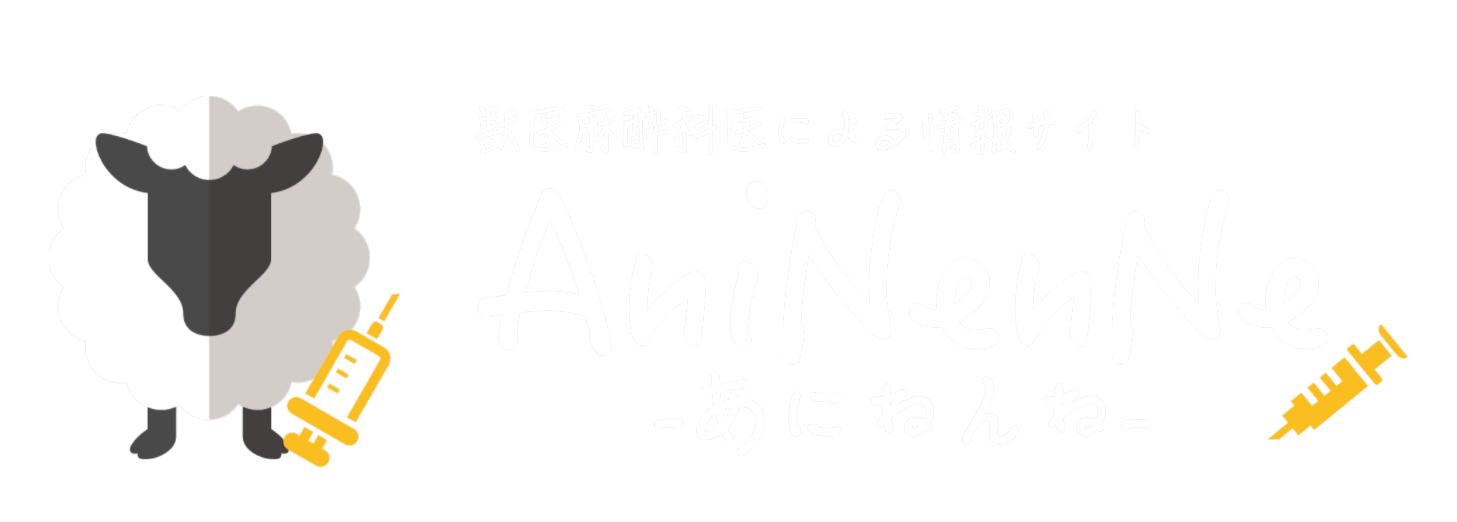獣医における麻酔は基本的な流れとしては、ヒト医療における麻酔と同じであると他の記事で説明いたしました。

しかしながら、全く同じわけではもちろんありません。大きく違う点がいくつかありますので説明したいと思います。
様々な患者に麻酔をする
これが一番大きな違いになると思います。
動物種は様々
最低限だと扱う動物種は犬猫のみですが、それでも2種類の動物です。犬と猫は全く違う動物種です。
日本の獣医の麻酔科医で牛や馬といった大動物も麻酔をかける人はあまり多くは無いですが、海外の麻酔科医は大動物ができないと麻酔科医とは呼べないと言っても過言では有りません。
米国の麻酔専門医の基準としては絶対に麻酔ができないと動物種はコアアニマルと呼ばれており、犬・猫・馬・反芻獣(牛・ヤギ・羊等)です。
その他の動物種に関しても麻酔科研修医中にある一定数麻酔の経験をしなければなりません。その他の動物種には鳥や、爬虫類、魚類や、げっ歯類、動物園動物も含まれます。
それぞれの動物種において、同じ哺乳類であったとしても体の構造は異なります。陸上の哺乳類と海棲哺乳類(イルカ、オットセイ等)はもちろん違いますし、さらに哺乳類と爬虫類だと様々な生体機能が違います。
患者の大きさが様々
先程述べたように動物種がばらばらであると、それに伴い患者の体重も様々です。
私の麻酔経験だと、小さい患者だと40gのハムスター、大きいものだと1トンの重種馬です。これだけ違うと寝かせ方も異なりますし、薬の量はとんでもなく違います。例えば寝かせるために、1kgのチワワだと0.5mL程度で済むプロポフォールという薬でも、1トンの馬だと300mL投与しなければなりません。投与するだけで、大変な作業になります。
また同じ動物種でも大きさもばらばらです。
例えば犬に関しては70kgのセントバーナードから、1kgのチワワまで麻酔を安全にかける必要があります。さらに、必要があれば1kg未満の子犬にも麻酔を掛ける必要があります。
病気も様々
獣医医療においても、開胸が必要な外科や脳外科、整形外科、最近では腹腔鏡等様々な治療が行われていますが、小児や心臓、脳外科専門の麻酔科なんてありませんので、どんな症例にも麻酔科医は対応する必要があります。
様々な動物種、大きさ、病気の患者に麻酔をかけなければならない
検査でも鎮静・麻酔が必要
鎮静や麻酔が必要な処置がかなり多いです。その理由を説明いたします。
なんで処置が必要か本人はわからない
動物はヒトの言葉で説得することが不可能で、なんで検査や手術を受ける必要があるのかわかりません。そのため検査等においても鎮静処置が必要なことが多いです。
採血をするだけでも患者によっては攻撃行動(噛み付く、引っかく等)を行いますし、動物種によってはその攻撃行動が人間にとって致命傷となることもあります。
また、ちょっとした傷の処置であっても、痛いところを触れば動物にとっては攻撃されたと思われても仕方ないことです。結果として攻撃的な反応をみせる動物もいます。そういった場合も鎮静処置が必要になるのです。
ただ鎮静・麻酔薬が毎回検査のたびに必要になると大変ですので、トレーニング可能な動物であればペットであればトレーニングをすることをおすすめします。動物園においても、検査をしやすくするために可能な限りトレーニング(ハズバンダリートレーニング等)を行っています。
じっとできない
動物に長い時間じっとすることを指示することはとても難しいです。CTやMRIといったしばらくじっとしていないといけない検査では麻酔が必要です。これらの検査においては呼吸を止める必要がある場合もあり、その場合は麻酔薬が必須となります。呼吸を止めるということを指示することはヒト以外の動物にはできません。最近状況により、無麻酔CT検査を行うこともありますが、特殊な症例およびCTの中でも上位機種が必要となります。またレントゲンの検査においても、しっかりとした評価をするために撮影する場合、鎮静薬が必要になることもあります。
処置が患者にとっては攻撃に感じてしまうこともある
ヒト以外の動物種には完全に動かない指示は難しく、麻酔薬が必要
麻酔科医がいなくても麻酔が必要
麻酔科医が所属している病院はほとんどありません。理由は他の記事で記載しましたが、獣医麻酔科医がほとんどいないからです。

ただし、鎮静や麻酔が必要な処置は獣医医療において数多くあります。先程あげたように、検査において鎮静・麻酔の処置が必要です。
さらに、避妊・去勢手術はどこの病院でも行うため麻酔処置が必要です。それだけではなく、脾臓摘出や、腸管吻合、椎間板ヘルニアの手術等も行う病院は多いです。そういった病院でも麻酔科医がいることは滅多にありません。この状況はヒトの病院に置き換えるとかなり異常です。咳の薬をもらう病院で手術は受けませんよね?でも動物病院では、手術を一次病院でする必要があるのです。
ではどうしているのかといいますと、病院によりますが、通常は他の業務も行っている獣医師が麻酔業務も担います。そして必要に応じて、動物看護師がその管理の手助けをします。手助けといっても獣医師が最終判断をするというだけで、看護師が重要なモニタリングをする必要性があり責任感のあるお仕事です。
最近は大学の授業において、麻酔の授業が必須になりましたが、以前は大学によりますがほとんど授業では扱われていませんでした。私が大学生のときに関しても麻酔の授業は6年間で合計4時間もありませんでした。そのため麻酔の勉強は、病院ごとに先生たちがセミナーに行ったり、麻酔科の人にアドバイスを貰ったりしながら行っています。
麻酔の需要に対して麻酔科医は少ない
獣医師・看護師が協力して麻酔は行っている
多くの制限
獣医医療の麻酔に関しては毎回ベストな麻酔ができるわけではありません。毎回ベストな形を作れることが良いですが、そうでない理由を説明いたします。
お金の制限
獣医医療は医療と比べると治療費をかけることができません。獣医医療において治療費は、様々な処置において何かを決める際に大きな要因の一つとなります。
その理由としましては、ヒトの様な保険が適用されませんので飼い主様の10割負担となるからです。手術費用だけで治療費が沢山必要なので、麻酔に費用を多くかけることができないことも多いです。なので結果として「なるべく安く、安全な麻酔」を目指す必要が出てきます。お金をかければかけるほど良い安全な麻酔になるかというとそうではありませんが、やはり値段の高い薬は存在します。そして治療費は病院によりますが、日本の治療費は他国と比較して安い傾向があります。それも相まりお金をあまり麻酔にかけられません。
もちろん飼い主様によっては費用がかかってもベストな麻酔をご希望される方も多いと思うので、そういった際にフリーランスの麻酔科医が依頼を受けるといった選択の必要性も今後出てくると思っています。またペット保険に関しても、今後よりサービスが良くなっていくと良いと思っています。
機材の制限
麻酔中に使える機材が制限されています。
それは先程あげたお金をかけられないということも一因です。
しかしそれだけではなく、人医療と比較して麻酔中に信用して使える機材が少ないです 。
例えば想像つきやすいのが血圧計です。血圧は麻酔において非常に重要な項目です。人間でも腕にまいて血圧を測ると思うのですが、その小さいバージョンを獣医医療では使っています。しかしながらそれらを使っても、毛や厚い皮膚のせいで測定を正確に行うことが難しいです。またミニチュアダックスフンドといった短足の犬種や、足の筋肉が一定の太さでないフレンチブルドッグ等の犬種においては測定が非常に難しいです。ダックスであれば尻尾に巻くことで血圧が測定できますが、強敵のフレンチブルドッグではそれも許してもらえません。
また脳波を測定することも厚い皮膚と毛のおかげで人間のようにはできず、獣医医療の麻酔において一つの大きな課題となっています。
ヒト医療に比べ、お金をかけられない
麻酔中に使用可能な機材が少ない
エビデンス(証拠)がないことも多い
獣医医療は発展してきていますが、エビデンスがまだまだ少ないのも現実です。
患者の絶対数がヒト医療と比べると圧倒的に少ないのが一番の原因となっています。
例を挙げると、ヒト医療では1000人の成人男性・女性のデータの論文がありますが、獣医医療においては100例の犬のデータでもかなり対象者の多い論文です。しかもこの100例の犬には違う犬種が含まれていることがほとんどであり、チワワもボーダコリーもゴールデンレトリーバーも一緒になっています。猫においては獣医学の歴史が浅く、さらにデータの数が少ないです。さらに言えば、オットセイなどの動物種はほとんどデータがありません。結果として、麻酔をある方法でかけて、その方法で患者が死ななければその方法が教科書に記載されることもあります。そういった情報を元に麻酔をかけなければならない場合は、その動物種の基本的な生体機能を知るために、しっかり生理学を学ぶ必要があります。
日本は小さい犬・猫が多いという特殊性を持っていますので、今後日本発信のデータを発表していき、より安全な麻酔を提供していけたらと考えてます。
飼い主様もまだまだ発展途中ということを理解してくださると幸いです。
獣医麻酔学はまだまだ発展途上
少しでも獣医の麻酔学に関して理解が深まっていただけたら幸いです。